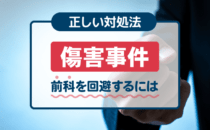傷害罪は親告罪ではない?|告訴とその取り下げの効果も解説
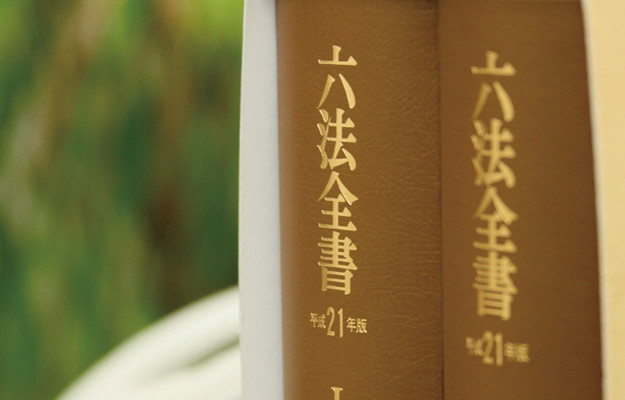
2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。
傷害罪は親告罪?
そんな疑問にお答えすべく、傷害と親告罪の関係を徹底的に解説していきます。
- そもそも親告罪の意味や種類とはなに?
- 告訴とその取り下げの効果、時効・被害届との違いは?
- どんな犯罪が親告罪なの?
この記事を読めば全部解決です。
親告罪の一覧もありますから、ぜひ最後までご覧ください。
法的な解説は、傷害事件に詳しいアトム法律事務所の弁護士にお願いしていきます。
よろしくお願いします。
親告罪か否かは被疑者にとって重要な意味を持ちます。
傷害罪が親告罪にあたるのか、その意味や種類、示談の効果などにも触れながら、解説していきます。
目次
傷害罪は親告罪?まずはこの「親告罪」の意味と種類から考える。
親告罪と非親告罪の違い
傷害事件が親告罪かどうかを考える前提として…。
そもそも「親告罪」とはどんな意味なのでしょう。
「親告罪」とは、告訴がなければ起訴されない犯罪のことをいいます。
また難しい言葉がでてきました。
「起訴」とは一体何なのでしょう?
「起訴」とは「検察官から、刑事事件について裁判所の裁判を求める申立てをされること」です。
日本では原則として検察官から起訴するかどうかを決められます。
これについて、刑事訴訟法の248条を見てみましょう。
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
出典:刑事訴訟法248条
検察官に裁量を認めるこの原則を「起訴便宜主義」といいます。
一方
「親告罪」とは、告訴がなければ起訴されない犯罪だとお伝えしました。
とすれば告訴の有無に起訴の可否が左右されるため、起訴便宜主義の例外だということがいえるでしょう。
逆に、「非親告罪」は告訴の有無に関係なく検察官が起訴できるため、起訴便宜主義を示しているといえます。
重要
親告罪は、告訴がなければ絶対に起訴されない!
また、親告罪には「相対的親告罪」と「絶対的親告罪」があります。
「相対的親告罪」とは、「犯人と被害者の間に、一定の関係がある場合に限って親告罪となるもの」をいいます。
逆に、関係性や状況に関係なく親告罪とされている犯罪を「絶対的親告罪」といいます。
この2つの具体例については、後で一覧にしてお伝えします。
| 相対的親告罪 | 絶対的親告罪 | |
|---|---|---|
| 意味 | 犯人と被害者の間に一定の関係がある場合のみ、親告罪となる。 | 関係性・条件に関係なく常に親告罪。 |
| 犯罪の例 | 窃盗罪など。 | 過失傷害罪など。 |
ところで、この「起訴しない」と検察官に決められることを「不起訴処分」といいます。
不起訴について詳細に記載した記事をご紹介しますので、ぜひご覧ください。
傷害事件における告訴とは?被害届との違い、告訴取り下げの効果。
傷害における告訴の意味に迫る。
今見たように、「親告罪か非親告罪かの違い」は、「起訴に告訴を要するか」という点でした。
さて…
この「告訴」とはなんでしょうか。
一度に似た言葉が多く出てきましたね。
丁寧に確認していきましょう!
「告訴」とは、犯罪の被害者その他の告訴権者から、捜査機関に対し、犯罪事実を申告して犯人の処罰を求められることをいいます。
告訴は捜査機関に口頭か、書面でされることになります。
「告訴権者」は「被害者」だけに限られません。
「被害者の法定代理人」も告訴が可能です。
未成年が傷害事件の被害者になった場合の「親」などがこれにあたります。
また
「被害者が死亡」した場合、「配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹」も告訴をすることができます。
もっとも、被害者が告訴しない旨を明示していた場合には、これに逆らうことはできません。
さらに、「死者の名誉を毀損した場合」は「死者の親族又は子孫」も告訴することができるとされています。
「親」は上でみたように「法定代理人」にあたります。
そして「法定代理人が被疑者(加害者と疑われている者)であるときは、被害者の親族が告訴をすることができるとされています。
大雑把ではありますが、これらの人が「告訴権者」の例になります。
傷害事件の場合
街中で殴られた、というようなトラブルの場合、被害者が警察に告訴するケースが考えられるでしょう。
傷害の被害届は告訴と違う?
このように殴られた人が警察に届け出る場合、「被害届」として受理されることもあります。
ですが、被害届は告訴とは異なるため、ご注意ください。
「被害届」とは、被害者が捜査機関に対して、犯罪の事実を届け出ることを指します。
「処罰を求める意思」までは必要とされない点で、被害届と告訴には違いがあります。
とはいえ、警察の捜査が始まるきっかけになる点では同じ効果を持ちます。
| 告訴 | 被害届 | |
|---|---|---|
| 相違点 | 処罰を求める必要あり。 | 処罰を求める必要なし。 |
| 共通点 | 捜査開始のきっかけになる。 | 捜査開始のきっかけになる。 |
告訴取り下げにはどんな意味がある?
被害届とは異なるこの告訴、実は後で取り下げることもできるんです。
刑事訴訟法では、告訴取り下げについてこう規定されています。
告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。
出典:刑事訴訟法237条1項
実は法律上は条文にあるように「取り消し」が正しい用語です。
ですが一般的に「取り下げ」と言われることも多いため、ここでは同じように表記します。
さて
告訴取り下げは「公訴の提起まで」とされていることが重要です。
つまり「起訴されるまで」しか取り下げることはできません。
ですが、取り下げられると大変重要な効果を発揮します。
それが…
重要
親告罪の告訴が取り下げられると、絶対に起訴されなくなる。
起訴には告訴が必要なのですから、取り下げられることで起訴もできなくなるということですね。
そのため
親告罪では被害者と示談を成立させ、告訴を取り下げてもらうことが特に重要になってきます。
そして取り下げは「起訴されるまで」にしかできないのですから、スムーズな示談の交渉・成立が重要といえるでしょう。
なおこの「示談」とは「トラブルの賠償問題を当事者間の話し合いで解決すること」をいいます。
示談金の支払いが注目されがちですが、交渉によっては告訴の取り下げも期待できるため、大変重要な意味を持ちます。
それ以外にも
告訴とその取り下げについて重要な特徴をお伝えしましょう。
重要
- ① 共犯者がいる場合、その一人に対して告訴をすると他の共犯者も告訴されたことになる。
- ② その後共犯者の一人について告訴を取り下げると、他の共犯者も取り下げられる。
- ③ 告訴は代理人がすることもできる。
なお、傷害事件と告訴の関係については『傷害事件で告訴されたらどうなる?|告訴後の流れや告訴状についても解説』で詳しく特集しているので、是非ご覧ください。
ではこのような告訴は、犯罪終了後いつまででもすることができるのでしょうか。
告訴期間とは?時効とは違う?
実は告訴はいつまでもできるわけではありません。
「告訴期間」という時間制限が定められているのです。
「告訴期間」とは、「親告罪について、告訴が有効にされる期間」を指します。
一定の場合を除き、「告訴権者が犯人を知った日から6か月」を経過すると有効な告訴はされなくなります。
「事件のあった日」からではない点に注意しましょう。
ここで、告訴期間の条文を見てみましょう。
親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。ただし、刑法第二百三十二条第二項の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第二百三十条又は第二百三十一条の罪につきその使節が行う告訴については、この限りでない。
出典:刑事訴訟法235条
「一定の期間が経つと告訴できなくなる。」
この点から、告訴期間が、時効とは違うのか疑問に思う方もいらっしゃるようです。
ですが、実は告訴期間と時効は違うものです!
この時効は、正確には「公訴時効」といいます。
公訴時効とは「犯罪後一定期間が経過することにより刑事訴追がされなくなる制度」をいいます。
期間の長さ、適用される犯罪の種類、起算点など、告訴期間とは全く異なる制度です。
公訴時効については、刑事訴訟法に規定があります。
1 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年
二 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年
三 前二号に掲げる罪以外の罪については十年
2 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年
出典:刑事訴訟法250条
殺人や強盗致死など、人を死亡させて死刑にあたるものには、公訴時効がありませんね。
ですがそれ以外の刑罰にあたる犯罪には全て公訴時効が定められています。
さらに、こちらは「犯罪後」一定の期間が過ぎることで完成してしまいます。
犯人が分からない場合、告訴期間は経過しませんが、公訴時効は経過していくことになります。
これらをまとめると…
親告罪と時効
- ① 「親告罪」で「告訴」があっても、「時効」が完成すれば起訴はされない。
- ③ 「親告罪」で「告訴」がなければ、「時効」が未完成でも起訴されない。
- ③ 「非親告罪」でも、「時効」が完成すれば起訴されることはない。
といえますね。
以上が告訴期間と時効の違いでした。
なお、傷害罪の時効については『傷害罪の時効|公訴時効、告訴・民事・慰謝料の時効は何年?』で詳しく解説しているので、是非ご覧ください。
| 告訴 | 時効 | 起訴の可能性 |
|---|---|---|
| あり | 成立 | 可能性なし |
| あり | 不成立 | 可能性あり |
| なし | 成立 | 可能性なし |
| なし | 不成立 | 不成立 |
傷害罪は親告罪なのか?
では傷害罪は親告罪なのでしょうか。
結論から申しますと…
結論
傷害罪は親告罪ではない!
となっています。
親告罪は条文に特別の規定がなければなりません。
ですが、傷害罪を親告罪とする規定はありません。
よって、傷害罪は告訴がなくとも起訴される可能性があります。
傷害罪でも、示談などの被害者対応は大切!
では傷害罪を犯してしまったらどうしようもないのでしょうか。
いえ、そんなことはありません。
先ほど述べた示談や告訴の取り下げも大きな意味も持ちます。
重要
「傷害罪」でも示談や告訴取り下げは大切!
示談金を支払い、民事上のトラブルが解決されれば、被害が一定程度回復したと考えられます。
また、告訴は「処罰を求める」という「被害者の処罰感情」のあらわれですので、「取り下げ」は処罰感情の低下を示します。
被害の回復や、処罰感情は、検察が起訴の判断で考慮する事項ですので、これらは不起訴の可能性を高めるでしょう。
また、示談により被害届を取り下げてもらうこともできるかもしれません。
軽微な怪我の場合、被害届を取り下げることで、立件すらされない可能性もあります。
被害者対応を迅速に行えば、さまざまな可能性が考えられます。
傷害事件を起こしてしまったときは、なるべく早く専門家に相談してみましょう。
傷害事件の示談については『傷害事件の示談金の相場|事件別に見る示談金の相場』にまとめているので、是非見てみてくださいね。
刑法の親告罪を全種類一覧にまとめます。
では、傷害罪と異なり、どんな犯罪が親告罪になるのでしょうか。
刑法犯における親告罪一覧をご紹介します。
刑法に規定される親告罪
まず、刑法に規定される絶対的親告罪の一覧です。
| 親告罪とする条文 | 罪名と条文 |
|---|---|
| 135条 | 信書開封:133条 秘密漏示:134条 |
| 209条 | 過失傷害罪:209条 |
| 229条 | 未成年者略取・誘拐:224条 未成年者略取等の幇助としての、被略取者引渡し等罪:227条1項 上記二つの未遂罪:228条 |
| 232条 | 名誉棄損罪:230条 侮辱罪:231条 |
| 264条 | 使用文書等毀棄罪:259条 器物損壊等:261条 信書隠匿:263条 |
つづいて、相対的親告罪を見ていきましょう。
ところで
「相対的親告罪」は犯人と被害者の間に一定の関係が必要とされています。
刑法では
相対的親告罪は、犯人と被害者が「配偶者、直系血族又は同居の親族」以外の親族の関係にある場合に親告罪とされる。
日本では民法725条で「親族」を「6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族」としています。
その中で、「配偶者、直系血族又は同居の親族」を除いた関係にあれば、親告罪となるのです。
参考に、日本における親族の表を掲載しておきます。

このような相対的親告罪には、どのようなものがあるのでしょうか。
一覧にしてみましたので、ご覧ください。
| 親告罪とする条文 | 罪名と条文 |
|---|---|
| 244条2項 | 窃盗罪:235条 不動産侵奪罪:235条の2 上記2つの未遂罪:243条 |
| 251条で244条2項を準用 | 詐欺罪:246条 電子計算機使用詐欺:246条の2 背任罪:247条 準詐欺罪:248条 恐喝罪:249条 上記5つの未遂罪:250条 |
| 255条で244条2項を準用 | 横領罪252条 業務上横領253条 遺失物横領罪:254条 |
いかがでしょうか。
横領や詐欺など、意外な犯罪も多かったのではないでしょうか。
以上が親告罪の一覧でした。
暴行・脅迫・有印私文書偽造など、親告罪と間違えそうな犯罪も多いですので、誤解がないようにご注意ください。
著作権や、強制わいせつ、強姦(強制性交等罪)など気になる犯罪と親告罪の関係。
なお、親告罪は昨今大きな変更がありました。
そこで、最後に非親告罪化についてお伝えしましょう。
たとえば、強姦罪や強制わいせつ罪はかつて親告罪でした。
しかし
改正により非親告罪となりました。
この重要な改正については以下の記事を参照してください。
また、凶悪な事件発生を機に、ストーカー行為についても非親告罪となりました。
こちらは刑法ではなく、ストーカー規制法に定められています。
また、違法ダウンロードなど著作権関連も非親告罪化が話題になっています。
TPPの締結など、不透明な部分も多いですが、これからも注目していく必要があるでしょう。
盗撮事件について、弁護士に相談。
スマホから弁護士に相談する!
以上、傷害事件と親告罪について見てきました。
傷害事件は親告罪ではありませんでしたが、示談や告訴取り下げは他と同様に大切だと知っていただけたのではないでしょうか。
とはいえ、示談をどのように成立させるのか、普通は想像もつきませんよね。
そこで
傷害事件における示談などについて、弁護士に無料で相談できる窓口をご紹介します。
なんとあのLINEで盗撮について弁護士に直接相談することができますよ。
具体的な事情を書き、どう活動すべきかを相談してみましょう。
刑事事件でお困りの方へ
ご希望される方はこちら
24時間365日いつでも全国対応
※無料相談の対象は警察が介入した刑事事件加害者側のみです。警察未介入のご相談は有料となります。
広告主:アトム法律事務所弁護士法人
代表岡野武志(第二東京弁護士会)
LINEなら、24時間、365日、全国どこからでも相談を送ることができますよね。
しかも弁護士が直接、順次対応してくれるので安心です。
傷害事件の具体的な解決策を教えてもらえればありがたいですね。
しかも
この電話番号では弁護士との対面相談予約を無料でできるんです。
24時間予約が可能で、夜中でも専属スタッフが対応してくれるそうですから、困ったときはぜひ使ってみて下さい。
地元の弁護士を検索して相談する!
また、人によっては「近くの弁護士に実際会って相談したい」という方もいらっしゃるでしょう。
そんな方はぜひ下から検索してみて下さい。
ここに掲載されているのは
- ネット上で刑事事件の特設ページを持ち、刑事事件に注力しているか、
- 料金体系が明確であるか
という点からセレクトした弁護士事務所ばかり。
傷害事件と示談に詳しい弁護士事務所もあるはずです。
示談をスムーズに締結し、告訴を取り下げてもらうなど、さまざまな対応をしていきましょう。
最後に一言アドバイス
いかがでしたでしょうか。
最後にアトム法律事務所の弁護士からひと言アドバイスをお願いします。
傷害事件でも示談の締結や、告訴取り下げは大変重要です。
事件後すぐに示談交渉をすることで、「起訴される前に」告訴を取り下げてもらうことができるかもしれません。
時期が早いほど、弁護士がとれる手段は多いものです。
傷害事件の当事者になった場合は、すぐに弁護士にご相談ください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
傷害事件と親告罪について考えてきました。
すぐに適切な対応をするためにも、不安に思ったらすぐにスマホで無料相談をしてみましょう。
具体的な盗撮事件に即したアドバイスをしてもらえると思いますよ。
また全国弁護士検索でお近くの信頼できる弁護士を探すことも有効でしょう。
なお、本記事に記載したこと以外で逮捕前に知っておきたい情報は『逮捕されたくない人必見の正しい対処法|条件を知れば怖くない』にまとめているので、興味がある方はご覧ください。
それ以外にも関連記事をご用意いたしましたので、ぜひ見てみてくださいね。
傷害事件に関するご不安が、一日でも早く解消されるよう祈っています。